RESOLUTION Vol.09
カギはユーザー目線の追求!オンライン会議対応設備構築プロジェクトから考える
高品質なオンライン会議環境を実現する方法とは?
カギはユーザー目線の追求!オンライン会議対応設備構築プロジェクトから考える
“本当に簡単に使える”会議室とは?

オフィスの「会議室」は、対面・オンライン会議問わず日常的に利用されるからこそ、使いやすさが求められる場所です。では、「使いやすい」とはどのような状態を指すのでしょうか?
本記事では、社屋移転を機に「高品質な環境で自社社員のITリテラシーを問わず、簡単に利用できる」会議室を妥協することなく追求し、実現したお客様との軌跡をご紹介いたします。
「重要な会議室だからこそ、運用も品質も高水準を両立したい!」
きっかけは、弊社が主催した会議室ソリューション紹介セミナーでした。新社屋への移転を控えていたお客様は、セミナーで体験したオンライン会議専用機の使いやすさ、シーリングマイクの高品質な音声や、カメラと連携した話者自動追尾機能に興味を持たれ、「社員が誰でも簡単に使える役員会議室を構築したい」とご相談をいただきました。
要件は次の通りでした。

- 社員の誰もが簡単に使える
- 会議準備を簡略化したい
- 会議中の操作を減らしたい
- あらゆる会議に対応したい
- オンライン会議(Google MeetやMicrosoft Teams 、Zoom)
- 対面会議(無線・有線での資料共有)
- 重要な会議室にふさわしい品質
- 発言者が誰なのかひと目で分かる
同社は今まで、会議用PCにカメラやマイクを都度接続・配置してオンライン会議に参加する方法をとっていました。セミナーで見た会議室用ソリューションを取り入れることで、会議準備や会議中の操作が削減され、同社の社員が簡単且つ高品質なオンライン会議ができるようになればという思いからのご要望でした。
ITリテラシーのレベルが異なるユーザーをさまざまな場面でサポートしてきたオンライン会議のご担当者から語られる「誰もが簡単に」という言葉にすべてが込められているように感じ、何としてもご要望を実現できるソリューションを提案しなければと、気を引き締めて臨みました。
理想の会議環境のデザインへ!現実(仕様・運用)とのギャップを乗り越える
お客様の新しい役員会議室のイメージは、セミナーで体験した機材を取り入れた「誰でも簡単にオンライン会議に参加できる会議室」と明確でした。
しかし、希望する機材をお客様の運用環境に合わせて導入するには、乗り越えるべき課題がありました。
【ギャップ1】今まで通りの使い方では性能が発揮されない?
「会議準備時間が短縮でき、マイク位置やカメラ操作を気にせず使える」― お客様にとって、天井常設型のシーリングマイクとカメラによる連携は、会議の効率化と高品質を両立できるソリューションでした。
しかし、同社の役員会議室は社内で最も規模が大きく、用途に応じてテーブルや機材の配置を変更しながら利用されてきました。新社屋でも多目的での活用が予定されていました。
シーリングマイクは予め設定したエリア内の音声を集音するソリューションで、固定されたレイアウトでこそ性能を発揮します。また、話者追尾機能はシーリングマイクで集音された音声を検知し、予め登録しておいた画角に合わせてカメラが動きます。レイアウトが変わって設定範囲から外れた場所で発言した場合、音声品質の維持や話者追尾機能の利用ができなくなります。

2台のシーリングマイクに設定した範囲内の話者の音声を集音し範囲外のノイズを抑制。範囲内の話者の声をクリアに届けます。
さらに、設定した集音範囲内で音声を感知すると、登録された画角に合わせてカメラが自動で動作。カメラから遠い席の発言者の姿もしっかりと捉えます。
【例】
設定された集音エリア内の●で発言すると、□(赤枠の箇所)の方向にカメラが動く
レイアウト変更からオンライン会議接続までの一連の作業に15分を要していたお客様の現環境を考えると、いかにユーザーの作業を減らし利便性を上げるかは重要なポイントです。
日常的にレイアウト変更が発生する運用スタイルでも、マイク位置やカメラ操作を気にせず高品質な会議ができる方法はないか?―弊社技術部門と検討したところ、専用のソフトウェアを使ってシーリングマイクの集音範囲を複数パターン登録し、会議のたびにパターンを切り替える方法があるとわかりました。シーリングマイクの集音範囲のパターンが定まれば、それに合わせてカメラの画角を複数登録しておくことが可能です。
そこでお客様に、オンライン会議で利用する会議室レイアウトの種類を限定し、レイアウトごとに集音範囲を切り替えながら利用することを提案しました。検討の結果、オンライン会議であれば2パターンにまで絞り込みが可能とご判断いただき、お客様のオンライン会議利用ルールとして組み込める運用が実現しました。
【ギャップ2】思い描いた使い方は本当に実現できるのか?
「定着した運用のもとメインツールが今より簡単に使えたら」―オンライン会議の運用ご担当者に共通する願いです。
お客様は、メインツールであるGoogle Meetの専用機「Google Meetハードウェア」の導入を強く希望されていました。
Google Meetハードウェアは、Googleカレンダーと連携させ会議を予約すれば、専用のタッチパネル上の会議情報をタップするだけでGoogle Meetの会議に参加できます。さらに、会議ID入力によるZoomへの接続や、会議用に持ち込んだPCと専用機の音響・映像設備(モニター、マイク、カメラなど)を連携させる「BYOD接続」にも対応し、Microsoft Teamsなどのオンライン会議が専用機と同等の品質で利用できます。
Google Meetハードウェアは、1台であらゆるオンライン会議が簡単に参加できる理想的な機器である一方、Microsoft TeamsやZoomの専用機に比べて圧倒的に情報が少なく、仕様通りの動作が可能かも不明な状態でした。
特に今回のような品質重視の会議室に導入する場合、外部の映像・音響機器と連携させるため慎重に検討を進める必要があります。
そこで弊社は、Google Meetハードウェアでお客様の希望する利用方法が実現できるかを徹底的に検証し、不明点をひとつずつ解消していきました。

検証事項は、
- Googleカレンダー連携時の動作
- Zoom接続時の挙動
- シーリングマイク・カメラとの連携
- BYOD接続時の動作
など多岐にわたりましたが、安心してGoogle Meetハードウェアが導入いただける基盤を整えることができました。
さらに、資料共有やBYOD接続をワイヤレスで実現できる機材として、無線映像伝送装置を取り入れ、お客様が挙げられた要件を叶える機材を揃えることができました。
【ギャップ3】やりたいことを叶えると簡単に使えなくなる?
お客様の希望する使い方ができる機材が揃ったとしても、簡単に使いこなせる状態であるとは言えません。
シーリングマイクによる正確な集音、カメラ操作モードの切り替え(自動・手動)、多様な会議ツールへの対応、資料共有(有線・無線)―会議室の機能が充実するほど、必要な設定作業が増えます。
シーリングマイクとカメラの設定切り替えにはそれぞれ専用のソフトウェアが、会議で利用する機器(専用機・BYOD、有線・無線)の切り替えにはスイッチャーが必要です。会議のたびPCでそれぞれカメラ・マイクの専用ソフトウェアを起動して設定変更し、機材ラック開けてスイッチャーを操作する必要があります。
この一連の作業はユーザーにとってハードルが高く、設定間違いなどトラブルの原因になることが想像できました。かえって現在の運用よりも参加までの手順が複雑化し、最重要視していた「誰にでも簡単に使える」運用からかけ離れてしまいます。
機能面はそのままにユーザーが迷わず各種設定を呼び出し、利用機器の切り替えができる仕組みを作れないか?― 弊社技術部門と協議を重ねたところ、視認性に優れた物理ボタン式のデバイスと組み合わせて会議に必要な設定ができるプログラムを組む案が出ました。
お客様の運用に合わせ、直感的に選択できるシンプルなデザインを各ボタンに割り当てることで、ユーザーは①会議の種類②レイアウト(集音範囲)③カメラ操作方法の順にボタンを押すだけで会議設備に関する設定が完了できます。
設定に必要なボタンのみで構成すれば誤操作やそれに伴う管理者負荷の軽減にもつながり、ユーザー・管理者両者にとってシンプルな運用が可能です。
オンライン会議への参加手順の変化(例:Google Meetの場合)

当初、専用のタブレットを別途用意して制御システムを構築する案もありましたが、物理ボタン式の方が構築コストをおさえられることや、Google Meetハードウェアの操作用タッチパネルと並んだ時に用途の違いが見た目で分かりやすくなると判断しました。
そして、シーリングマイク・カメラ・会議室機材の設定切り替え操作を一元化し、ボタンを押すだけで完了できる利便性の高さをご評価いただき、導入が決定しました。
| 機材で会議室に必要な機能を整える | |
|
|
 |
Google Meetハードウェア |
 |
シーリングマイク+カメラ |
 |
無線映像伝送装置 |
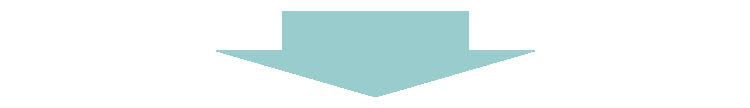
社員が迷わず会議に必要な設定ができる
オンライン会議はもちろん、室内の機材を簡単に利用できる会議室に

使い始めてからが本番。「使いやすい」会議環境の調整・維持へ
社屋移転が完了した現在、会議室は順調に稼働しています。ご担当者に共有いただいた明確なユーザー像のもと、使いやすさを重視した運用設計ができたことが順調なスタートにつながったと感じています。
その後、お客様よりレイアウトパターン追加のご相談をいただきました。会議室は、運用を重ねる中で用途や利用方法が変化することが少なくありません。今回のご要望も、実際に設備をご活用いただいているからこそ生まれたものでした。

お客様には弊社が提供する会議室設備の保守にご加入いただいています。保守メニューには導入後の機材設定の再調整が含まれており、今回のレイアウト追加時にご活用いただきました。導入して終わりではなく、運用の変化に応じて最適な状態を維持できるよう、機材だけでなく運用面まで含めたサポートが提供できるのは弊社保守の強みです。
今後もお客様の「誰でも簡単に使える会議環境」を支えるパートナーとして、運用支援に携わっていきたいと思います。











